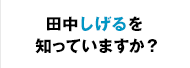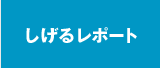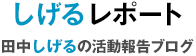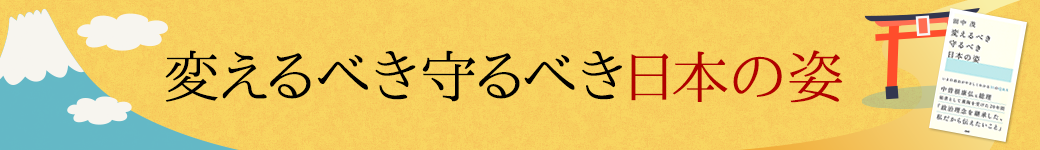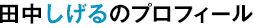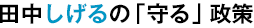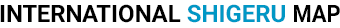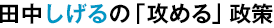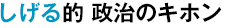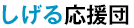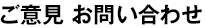『国民に苦痛を強いる財政改革を行うためには、政府が自ら勇断をふるった大行政改革を行わなければならない』
これは行政改革を断行する際の中曽根康弘先生の強い決意を示した言葉です。
徹底的なムダを排除し行政の合理化を図り、民営化や規制緩和を行い、増税によることなく財政再建を実現することが、中曽根内閣の重大な使命でした。
中曽根先生と言えば外交だけが注目されがちですが、内政での特筆すべき点は行政改革でした。
1981年、鈴木善幸内閣時代の行政管理庁長官であった中曽根先生は、経団連の元会長だった土光敏夫(当時80歳)氏に三顧の礼を尽くして第二次臨時行政調査会・会長に就任して頂きました。
土光会長は「増税なき財政再建」を行財政改革の基本として第二臨調の答申としたのです。
第二次臨時行政調査会は、別名「土光臨調」でも知られていますが、中曽根先生は土光氏を第二臨調会長にお願いした理由を以下のように述べています。
「この第二臨調は国民の協力を求めることが必要であったのです。それにはそれ相応の人に会長になってもらう必要がありました。普通の人を選んだのでは、この大事業はできないからです。そこで私は土光敏夫さんに会長を依頼しました。なぜなら、土光さんは清貧で高潔なお人柄であり、土光さんならばこの臨調の象徴となって、これを成し遂げることができると、そういうイマジネーションが私にはあったからです」。
1980年代、中曽根先生が行政管理庁長官に続き総理大臣に就任するや即座に「増税なき財政再建」の標榜のもとで行革に着手しました。
その背景には、土光氏の「民間がこれだけ血を流しているんだから、国家も流さなければいけない。だから『増税なき』でやれ。増税すれば、必ず経費を無駄遣いして役所が膨張するだけだ。それから3K(コメ・国鉄・健康保険)の赤字解消、そして特殊法人の整理、官業の民業圧迫を排除するなど民間の活力を最大限に活かす方策を実現してくれ」との切実な申し入れがあったのです。
これら3Kの中でも最大の牙城が国鉄分割民営化でした。当時、国鉄は毎年2兆円近くの赤字を出し補助金ももらい、それを国民の税金で埋めておきながら、ストライキばかりしていました。
コメに関しては、食料管理制度の赤字は1兆円(1980年代当時)にも達していました。
財政が悪化し続けていた「健康保険制度」改正においても当然ながら凄まじい抵抗がありました。それまでは本人の医療費がタダだったのを1割負担(現在は3割)にしたのですから野党を含め福祉団体や労働団体、そして日本医師会が反対し、国会の内外で激しい論議が展開されたのです。しかし実際に施行されたら乱診乱療が減少し、医療負担が顕著に少なくなっていったのです。
現在、国民皆保険制度の短期滞在の外国人留学生の問題とかありますが、当時の健康保険制度の本人負担導入の法改正は、内閣の一つや二つ飛んでも不思議ではないと言われた程の大問題でした。老人医療も全部無料だったのを少しでも本人に負担して頂くようにしたのですから…。健康保険制度、老人医療制度などを改正し、国民に負担を強いました。政治家ならやりたくない仕事といえます。
予算は単年度の話であり、抜本的な財政改革にはなりません。そこで予算に関連する制度や仕組みそのものを変えていったわけです。
石油ショック以来、経済構造が変わり税収は伸びないどころか落ち込んでいく。しかし社会保障費を減らすわけにも、景気を支える公共投資を減らすわけにもいかない。そのギャップを埋めるのに増税をしてはいけないわけですからこんなにつらい話はありません。
このような状況の中で、結局、行財政改革全体を進めていくためには、先ずは徹底的に歳出を押さえたのです。
以前、私のコラム(2025/03/28 内閣総理大臣の資質 ー大蔵省(現・財務省)「予算編成権」奪取で見る中曽根政治ー)でも紹介していますが、そこで中曽根内閣の5年間は予算編成にあたり、各省から出てくる予算の要求に対し、予算要求の上限”シーリング”を厳しく抑え込んだのです。
中曽根内閣の初年度(昭和58年度)の予算編成に当たって、経常経費は前年に比べマイナス6%、投資的経費は0%と、要求自体を前年以下に抑える枠をはめて、それから予算査定でさらに削り込んだのです。59年度からはさらに強化して、経常経費はマイナス10%、投資的経費もマイナス5%としました。
中曽根内閣の最後の予算編成は5年後の62年度でしたが、58年度から62年度までのまる5年間、マイナス・シーリングで通したのです。つまり国の一般会計予算のうち、建設国債は国民の財産として残るのでいいのですが、削るわけにはいかない国債の利払い償還費と地方交付税を除いた一般歳出の伸びを前年よりマイナスにしたのです。
国全体の予算を実質的に減らすわけですから、強烈な指導力がなければ出来ません。
明治以来、石破政権までの間、このような内閣が他にないこと自体驚くべきことです。
行政改革というのは中曽根先生の内閣一代でできるものではありません。いつの時代でも断行すべき課題です。当然、先生は第二臨調の次のプランを考えていました。それが行政改革審議会(行革審)でした。つまり第二臨調で答申したものを監視、点検し、さらに出てくる新しい問題を推進させるという発想だったのです。
中曽根先生は行財政改革を行うときには、大臣を任命する際に「君を大臣にするが、私が断行する行財政改革に協力するか、私のいうとおりに一生懸命やるか」と尋問し、みんな大臣になりたいので「はい。必ずやります」と、その言質を取っておいたそうです。そのようなことを行った初めての総理大臣でもありました。
国鉄改革では、国鉄や運輸省内部、そして郵政改革の一環で電電公社を改組してNTTをつくる際にも、強硬に反発するいわゆる族議員や官僚がいました。
先生はその様な反対を抑えるために閣議で「私の方針に反対する官僚がいたら左遷するから、大臣の諸君もよく心がけておいてくれ」と厳命したのです。それを記者会見でも述べたので、みんな先生の方針に従った訳です。
先生は官僚と敵対するのではなく説得すべきであると述べつつも、次のように続けています。「官僚ははじめのうちは様子を見つつ総理大臣や政治家を軽視する性格があります。だから最初の決断と行動が肝心なのです」。
中曽根先生の行政改革は、官僚制を改めるとともに族議員からも余計な干渉を受けないという政治をやり遂げることでした。
中曽根先生は行政改革の工程管理表については、次のように言及しています。
「石油危機が1973年と1979年の二度おこり、民間の会社は土地や工場を売ったり、あるいは辛い人員削減をやったりしながらその危機を乗り切るために血の滲む努力をしてきたのです。
労働組合もそれにしたがって、ストライキなど起こさずに会社の再建を優先させてくれました。
これだけ国民の皆さんが苦労するのだから、今度は政府の番だと。
そこで私は政府は補助金を切れ、あるいは人員も減らせと、そういうことをしたわけです。仕組みとか、やり方自体については、役人主導でしたら、また前と同じ轍を踏むことになりかねない。そこで今回は政治家主導、あるいは党主導でしなければならない。しかし、党主導といっても、党は族議員が多く、それはなかなか難しい。結局、政治主導、官邸主導でするしかありません。官邸主導でするには、いままでのものでは駄目であるから工程管理表をつくったわけです。
だから第一に、政府の機構については、だいたい何年度くらいに何をしていくか、目処を立ててる。その中には国鉄民営化、電電公社民営化も入るし、あるいは専売公社民営化も入ります。その大事業の前に、補助金を切り、そして次の予算編成のときに公務員のベースアップ(5年間)をやめる。給与を減らすというと、順次下げられてしまい事務次官以下みんな減ってしまう。それはかわいそうだから、彼らの場合は昇給をストップさせ、減らすということはしませんでした。国家公務員よりも地方公務員の給与が高かったのでラスパイレス指数(加重平均物価指数)を作り、高いところは引き下げさせました。
そのかわり大臣の給料を一割減らす。またカットした分の大臣の給与は国庫に返そうとしましたが、法律上それが出来ないので、日本赤十字社に寄付しました。そのようなことを私の在任期間の5年間、計画的に工程管理表をつくって指示しました。
これが済んだから、今度はいよいよ国鉄改革。その次が電電公社です。それから、それと前後して円ドル関係をきちんとして、日本の金融の開放をしなくてはいけません。そのため、日本の金融市場の開放、ビックバンの前哨戦を私のときにしました。これも大蔵省がかなり渋りましたが、金融市場開放の工程管理表をつくれと命じ、これには大蔵省がびっくりしました。いったいどういうふうにつくったらいいのかと、主計局長や理財局長が連日、私に訊きにきました。だから、これこれ、これこれで、こうやるのだと、そういうことをいったのです。また当時の大場智満財務官を督励して、何回もアメリカへ行かせて、米国財務官のスプリンケルとやり合わせました。
そのようにして工程管理表をつくりあげたのです」。
中曽根先生はこのような行革の成果を国民に示しつつ、中曽根内閣最後の年に税制の抜本的改革となる直間比率の見直しと売上税を推進しました。しかしこれは国民の反対を受けて成功しませんでしたが、政権を受け継いだ竹下内閣の下で、消費税として制度化され今日に至っています。
そもそも官庁や官僚は、民間企業やそこに勤める人と構造的に異なり、利益を上げることが活動の目的ではありません。
また利益を上げなければ倒産する企業と異なり、国が滅びない限り身分は守られています。いきおい、その目的は国からできるだけ多くの予算を取り、自分たちの権限を大きくすることに向けられがちになります。
国の予算の原資は国民の税金です。だからこそ無駄を省くための行政改革に決して終わりはなく、いつの時代でも常に推進していかなければなりません。
政府が増税だけを唱え、行政改革を断行しない限り、国民にはまた借金のしわ寄せを一方的に押し付けられたという不満が残るでしょう。ましてや財政規律を唱えながら増税を行い公務員の給与を上げるのでは、国民は納得しないどころか怒りを覚えます。また増税は政府支出の拡大を助長し、財政規律の弛緩をもたらすかもしれません。
そのためにも行政改革を断行する際には、中曽根行革のように計画性を持ち用意周到にすべきです。国鉄・電電・専売の民営化は、これを実行する民間のトップに土光氏を据え、工程管理表を作成し、そのプロセスを中曽根先生自ら、または様々なメディアを通して国民に逐一説明するなど極めて計画的に行ったのです。
そして何よりもその目的を国民に明確に示しました。すなわち国の無駄を省き、規制を緩和し産業をより興し、国民を豊かにして、外国の国々との国際競争にも十分勝てる国家を目指す、というものでした。
新しく就任した高市早苗内閣総理大臣には、総裁選で表明したことを具体的に実現して頂くためにも、揺るぎない使命感を持ち強烈なリーダーシップを発揮して頂きたいと切望します。